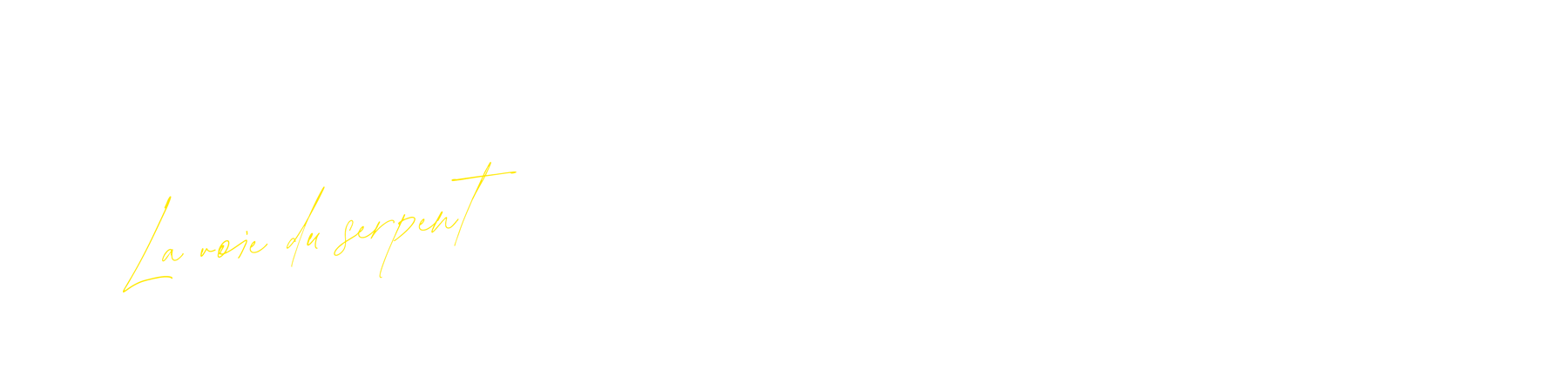黒沢清監督、
26年を振り返る
Vシネマで自分が思う
娯楽映画を追求
――『蛇の道』を撮影していた26年前を振り返ったときに思い出すのはどんなことですか?
前年には『CURE』(97)がありますが、『復讐 運命の訪問者』(97)、『復讐 消えない傷痕』(97)の2本、『蛇の道』や『蜘蛛の瞳』は、実はVシネマ(オリジナルビデオ作品)で、低予算でタイトなスケジュールとはいえ、やりたいことができて、それなりに手応えがあったのを覚えています。でも、それだけです。作った後、自分の作品がどうなるのか? なんてことはほとんど考えませんでした。
――いま言われた「やりたいことができた」というのは?
僕はそのころ、自分の能力も含めて、日本では予算のことだけではなく、さまざまな要因で娯楽映画がそう簡単には作れないということを痛感していました。『地獄の警備員』(92)は完全に娯楽に振ったものだったんですが、こういう映画はもう撮れないんだな?って思っていましたし、かと言って、完全に作家性に振った作品を作るのも少なくとも商業映画では難しくて。そんなときに「Vシネをやらない?」って声をかけてもらったんです。最初は、哀川翔さん主演のヤクザものを自分に撮れるのか、全く自信はなかったんですよ。だけど、やってみたら楽しくて。ハリウッド映画に代表される圧倒的な娯楽作品とは違う、マニアックな世界観ではあるものの、娯楽を追求していいという環境でしたし、それが自分が思う映画を商業ベースでギリギリ撮り続けられるのではないか、という希望にもなりました。
――その直後に、Jホラー・ブームが巻き起こります。
ええ。ホラー映画はもともと好きではありました。なので、ホラーの演出に長けていたわけではないので最初は不安でしたが、Jホラーという枠でも頑張ればギリギリ娯楽映画が作れると信じて何本か撮らせていただきました。
――『CURE』の成功がJホラーを撮るきっかけにもなったのでしょうか?
いえいえ、さっきもお話したように、撮っているときは「面白いカットが撮れた。上手くいった」といった小さな手応えはありましたが、後に「僕の代表作」だなんて評されるとも思っていませんでした。東京国際映画祭で役所広司さんが最優秀男優賞を受賞しましたが、主だった賞はそれぐらいで、お客さんも全然入らなかった。ただ、Jホラー・ブームで『CURE』に再びスポットが当たって。脚光とまではいかないですけど、少しだけ認められたんです。


『ニンゲン合格』で得た
喜びと痛み
――ホラー映画を撮っているときは、それ以外の作品も撮りたいという欲求や撮れない苦悩もありましたか?
僕もホラー映画は好きですけど、ホラーだけがやりたいわけではないので、その葛藤はありました。
――トビー・フーパー(『悪魔のいけにえ』などで知られるアメリカのホラー映画の鬼才)みたいになっちゃうんじゃないかという恐れも?
それもありましたね。トビー・フーパーに会って話を聞いたときも「そんな企画ばっかり来るんだよ。ホラーじゃないものもやりたいのに」って本当に辛そうな顔をしてましたけど、ホラー映画はどこかそのジャンル専門の監督が撮っていると思われがちで、映画のいろいろなジャンルの中にホラー映画もあるという認識のされ方がなかなかされない。ホラー映画を量産している監督たちも、本当はほかのジャンルを撮りたいんです。
――黒沢監督がそこから抜け出すように撮った最初の非ホラー映画は『ニンゲン合格』(99)でした。
『CURE』、“復讐シリーズ”、『蛇の道』、『蜘蛛の瞳』と陰惨な作品が続いたので、人がバタバタ死ぬものではなく、「家族を扱ったものをやってみよう」という話になって、オリジナルで脚本を書いたんです。そしたら、わりとすんなり企画が通って、撮影も気持ちよくできたんですけど、大ヒットするような映画でもないですし、評価もされませんでした。東京国際映画祭のQ & Aのときの、最初の方の感想はいまでもよ~く覚えています。その人は「『CURE』のような映画を期待していたのに、全然違っていたから、ガッカリしました」って言ったんです。あまりにも露骨な感想だったので、思わず「すみません」って謝っちゃいましたけど(笑)、そのときに陰惨な映画を何本も作っていた監督が全然違うジャンルの映画を撮ると人は戸惑うんだなっていうことを学びました。“周りが勝手に作り上げたイメージに負けて、その呪縛から抜け出せずにいると、トビー・フーパーのように同じような映画ばかりを撮り続ける苦悩を味わうことになるんだな、危ない、危ない!”といった思いにもかられたような気がします。『ニンゲン合格』を作ったことはとってもいい思い出です。けれど、作った後は何ひとついいことはなかったですね。


ほかの人の脚本は
受け入れられない
――『ニンゲン合格』はホラー映画ではないですけど、黒沢さんらしさが随所に感じられる映画でした。
自分らしさが出てるのか否かは自分では分かりませんが、あのころは依頼される企画が偏ってしまうのではないか? という危機感があったので、可能な限り、いろいろなジャンルのものをやることを心がけていたんです。ただ、ここが僕の特徴でもあるし、弱点だと自覚しているんですけど、『復讐 運命の訪問者』や98年の『蛇の道』のシナリオをオリジナルで書いてくれた高橋(洋)くん以外、他人が書いた脚本で上手くいった試しがなくて。もっと他人の書いた脚本をそのまま受け入れることができたら、よくも悪くも作品の幅も広がったんでしょうけど、それができない。「こんな脚本なんですけど、やりませんか?」ってプロデューサーに話を振られ、「酷い脚本ですね。書き直してもいいのなら、やります」と言って、実際にすべて書き直して撮った映画もあるんですけど、なかなかそのまま受け入れられない。そこが僕の欠点だと思いますし、だから作品の傾向も偏ってしまうんです。
――ほかの人が書かれた脚本のどんなところが受け入れられないんですか?
娯楽映画になってないですよねってことです。映画の娯楽って何なの?ってことがまったく追求されてない、浅はかとしか思えない脚本が多いんです。だから別に、僕は自分の好みや自分の世界観でほかの人の脚本を直すわけじゃないんです。映画の原理に則って「これはダメ」と言っているので、余計にたちが悪いですけどね。自分に責任はないって言ってるわけですから(笑)。
――黒沢さんが思われる娯楽映画になっている、なっていないの基準は何ですか?
それを言い出すときりがないほどいっぱいあるんですけど、いちばん分かりやすいところで言うと映画における過去の扱いです。現在進行形で、次に何がある? この先どうなるんだろう? ということを次々に見せていくのが娯楽映画の最低原理。もちろん、なぜそうなったのか? という説明もした方がいいんですけど、説明は説明なので、その説明が面白いことはない。基本的にはつまらない。最も危険なのは推理モノですね。刑事や探偵が「実は昔こんなことが起きたんです」と奇想天外な事件の概要を語ったところで、全く面白くない。その形式で面白い映画って、たぶん1本もないと思います。なのに、未だに過去こそが面白くて、現在は全く面白くないという作劇のものが多いから困ったものです。
――黒沢監督は昔から「映画は現在進行形」って言われていました。
ただ、そのセオリーを絶対に守らなきゃいけないということでもないから、映画って怖いんです。セオリーから出発したいけれど、踏み外すこともあるし、全く踏み外しているのに面白いものになることもたまにある。そこが映画の底知れなさです。
――踏み外しているのに面白い映画って、例えばどの作品ですか?
脚本をちゃんとチェックしたことはないですけど、クリント・イーストウッドの映画なんて、相当型破りなことをやっているような気がします。観ているときは全然気にならないのに、後から冷静に考えてみると、よくこんな脚本で成立させたなって思うものもありますから。それに、映画は主演俳優が魅力的なら何でもいいという側面もあるし、それだけで脚本の欠点さえも乗り越えられるので、セオリーが絶対ではないということをつけ加えておきます。
――いま言われたような背景があったからなのか、黒沢さんは『大いなる幻影』(99)、『カリスマ』(99)、『アカルイミライ』(03)、『トウキョウソナタ』(08)などの一般映画と並行して、その後も『回路』(01)や『ドッペルゲンガー』(03)、『LOFT ロフト』(06)、『叫』(07)などのホラー映画を撮られていますね。
ホラー映画もやっていて楽しいですからね。ただ、やっていて楽しかったのも『LOFT ロフト』や“せっかく声をかけてくれたんだから頑張ろう”という気持ちで撮った『叫』が最後で。あとは声をかけてもらっても“どうしよう、もうネタがない。ありがたいけれど、ごめんなさい”という感じでした。あのころはJホラーのブームは日本でも去っていたので、このままやっていて大丈夫かな? という焦りもありましたが、昔のようなブームは過ぎ去ったものの、ホラー映画がいまでもさまざまな形で作り続けられているのは嬉しいですね。


女性の俳優の素晴らしさに
気づいた
――偶然かもしれませんが、それまでは男性の主人公が多かったのに、2010年ごろを境に、女性が主人公の作品が増えてきましたね。
自然な流れではあるんですけど、きっかけはありました。『トウキョウソナタ』を撮った後、映画が全く撮れない状態が数年続いたんです。幸いにもそのときに、WOWOWから湊かなえさんが原作の『贖罪』(12)のドラマのお話をいただいて。仕事がなかったので、「何でもやります」と言って引き受けたのですが、これが5人の女性がオムニバス形式で出てくるものだったから焦りました。女性を主人公にしたドラマは最も苦手なジャンルでしたし、それが5つも並んでましたからね(笑)。だから“どうしよう?”という感じではあったんですが、やってみたら女優さんが素晴らしくて。5人の女優さんのうちのひとりは以前から知っている小泉今日子さんでしたが、後の4人は蒼井優さんを含め、全く初めてだったので、ビクビクしながら始めたんですが、5人とも個性や雰囲気がまったく違っていたんです。まあ、当たり前のことなんですけど、そう改めて思いましたし、ある意味、男性より割り切りがいい。何でもやってくれる。尻込みをするんじゃないかな?っていう先入観があったんですが、あらゆる注文に答えてくれて。みなさん、普段のイメージに囚われることなく、その役に合った髪型やメイクで僕がお願いした通りの女性を作り上げてくれたんです。そんなこともあって、その後は僕が強く望んだわけでもないですけど、女性が主人公の原作モノの企画も自然にいただけるようになりました。『岸辺の旅』(15)や『散歩する侵略者』(17)などがそうですね。もちろん、男性の俳優にも素晴らしい人がいっぱいいるのは分かっています。『贖罪』で、どちらかと言うとそれまで苦手意識があった女性の俳優の素晴らしさにようやく気づいたというのが正しい言い方かもしれません。
――黒沢さんは近年、新しい映像表現にも挑戦されています。『スパイの妻』(20)を8Kで撮り、新作の『Chime』も動画配信のプラットホームで鑑賞される作品ですが、そのあたりもふまえて、映画や映像表現の未来をどのように考えられているのか教えていただけますか?
そこに関しては、いまはわりと楽観的に考えています。僕たちのような作り手は暗い映画館の大きなスクリーンでみんなで観る、昔からある映画の形式をひとつの理想形として作品を撮っています。ただ、自宅のモニターで観た人に「それは映画じゃない!」って言う人はもういません。しかも、ひと昔前は「映画はそれでもフィルムでしょ」という時代がありましたが、その時代も終わって、映画だろうがテレビ作品であろうが、撮影はすべてデジタル。映画とドラマは尺の違いはあるかもしれませんが、作る側もそれ以外のことは意識することなく、同じように撮っています。「これはテレビで放送するドラマだから、テレビっぽいものを目指してよ」なんてことを言うプロデューサーもいないし、ドラマを作っているみなさんも“いつか、この作品を大きなスクリーンで観れたらいいな”という憧れを持っている。そんな風に、現代でもまだギリギリ、映画館で観ることが映像で物語を経験する最良の形として残っている。俳優やスタッフもそれを夢みて、そこを目指して関わってくれているという実感もありますから、僕はやっぱりこれからもそこを目指します。一方では、ヘンな言い方かもしれませんが、デジタル化してくれて本当によかったと思っています。これで晴れて、映画もドラマも何の区別もなくなったと言えますから。