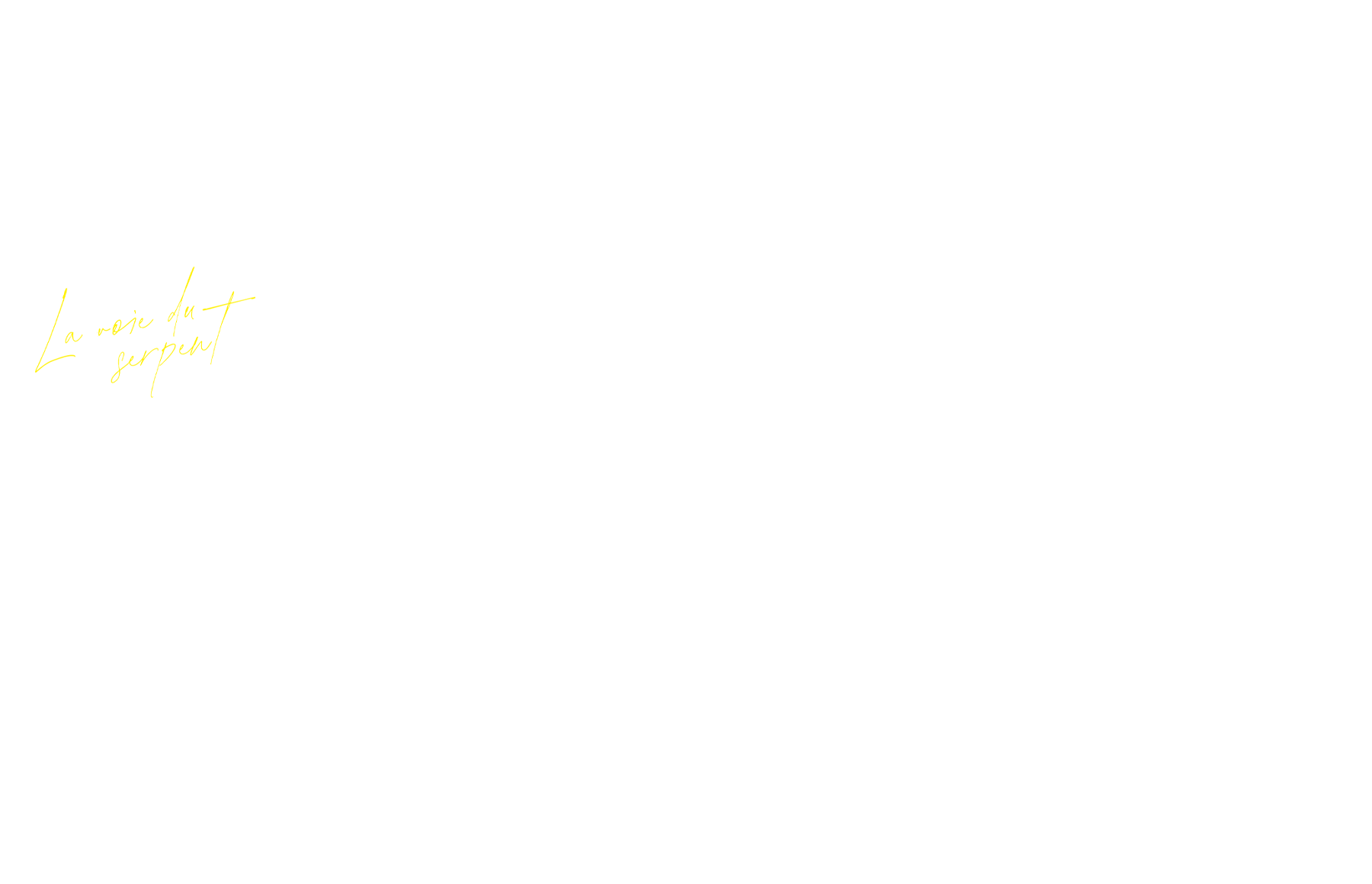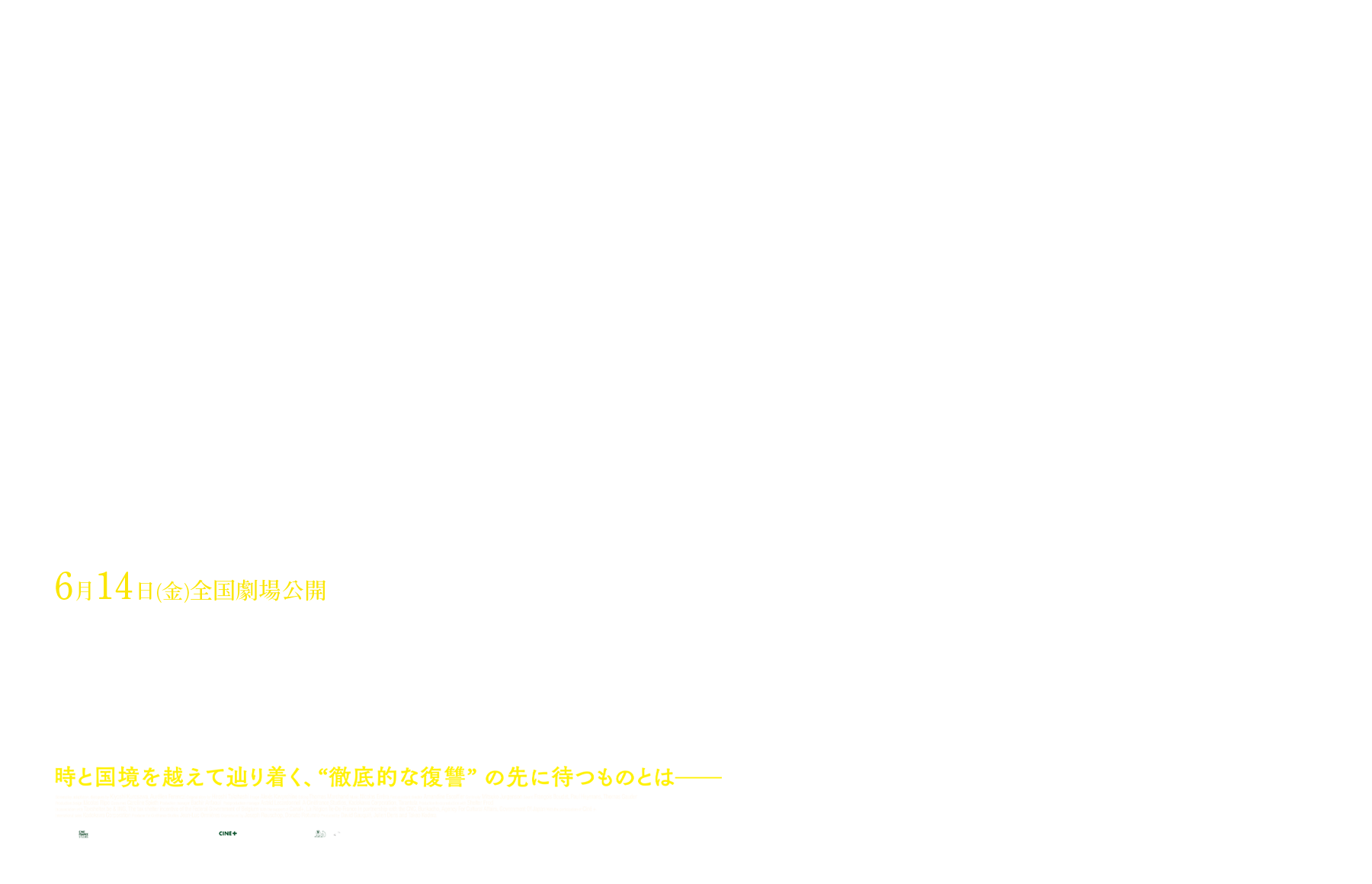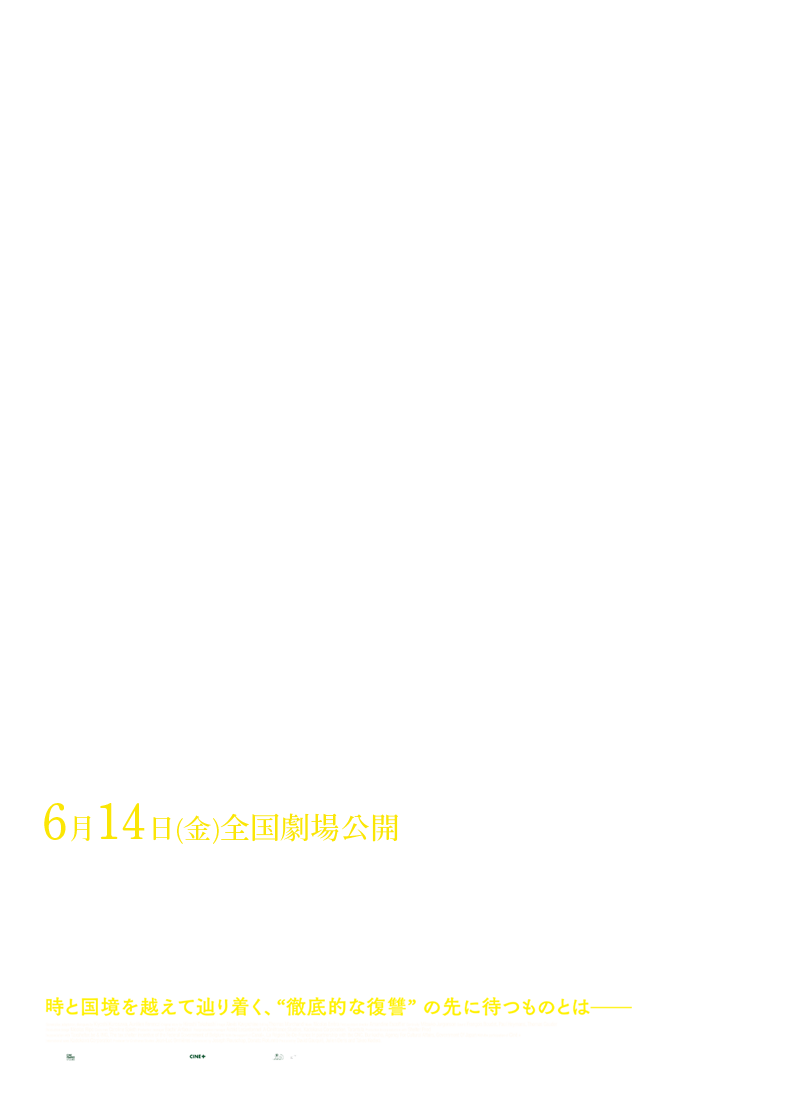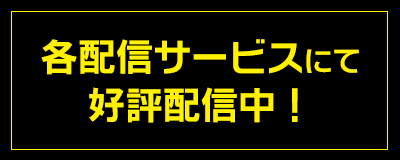Introduction
×
主演:柴咲コウ
完全版“リベンジ・サスペンス”
『蛇の道』は、そんな黒沢監督が、98年に劇場公開された同タイトルの自作をフランスを舞台にセルフリメイクし、自ら「最高傑作ができたかもしれない」と公言するほどのクオリティで放つリベンジ・サスペンスの完全版である。
8歳の愛娘を何者かに殺されたアルベール・バシュレは、偶然出会ったパリで働く日本人の心療内科医・新島小夜子の協力を得ながら、犯人探しに没頭。復讐心を募らせていく。だが、事件に絡む元財団の関係者たちを拉致監禁し、彼らの口から重要な情報を手に入れたアルベールの前に、やがて思いもよらぬ恐ろしい真実が立ち上がってきて……。アルベールの復讐に協力する小夜子に扮したのは、黒沢監督からの熱いオファーに応えて出演した柴咲コウ。NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」(17)でタイトルロールを演じ、『君たちはどう生きるか』(23/声の出演)、『ミステリと言う勿れ』(23)などの話題作への出演でも知られる彼女が、撮影の半年前からフランス語の厳しいレッスンに臨み、現地で2ヶ月間、実際に生活をして、パリで暮らす謎多きヒロインを完璧に自分のものにしている。
復讐に燃えるアルベールを演じたのは、第72回カンヌ国際映画祭コンペティション部門の審査員賞に輝く『レ・ミゼラブル』(19/ラジ・リ監督)で、フランスのアカデミー賞とも言われるセザール賞の主演男優賞にノミネートされた注目のフランス人俳優ダミアン・ボナール。さらに、『彼女のいない部屋』(21)などの監督としても知られるフランスの名優、マチュー・アマルリックが、黒沢監督がフランスで初めて撮った『ダゲレオタイプの女』(16)に続いて出演。『ネネットとボニ』(96)などのグレゴワール・コランと小夜子たちに拉致される財団の幹部に扮し、緊張感が支配する本作に独自のユーモアを持ち込んでいるのも見逃せない。日本からは濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』(21)、北野武監督の『首』(23)で世界的に注目を集め、黒沢監督とは5度目のタッグとなる西島秀俊が、心を病んだ小夜子の患者・吉村役で出演。米・アカデミー賞の視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』(23)、本年24年公開の『犯罪都市 NO WAY OUT』など国境を超えた話題作への出演で勢いに乗る青木崇高が小夜子の夫・宗一郎に扮し、本作の闇を一層深いものにしている。
また、セザール賞受賞歴もある撮影監督アレクシ・カヴィルシーヌはじめ『ダゲレオタイプの女』のスタッフたちが監督たっての希望で再結集しているのも注目のポイント。美しくシャープな本作の切れ味を、より精度の高いものにした。

Story
壁の鎖に繋がれたラヴァルの前に、無言のまま液晶モニターを運んでくるアルベール。スイッチを入れ、そこに少女が微笑むホームビデオが映し出されると、彼はようやく「僕の娘だ。殺された」と重い口を開き、「娘のマリーは財団関係者に拉致された。あなたがやった。そうですね?」と詰め寄る。 だが、ラヴァルは「私はやってないし、何も知らない」と嘯くばかり。イライラを募らせたアルベールは拳銃を彼の頭に突きつけるが、小夜子に「焦らないで。時間はいくらでもあるんだから」と言われ、銃を取り上げられると、ようやく平静を取り戻し、その場を立ち去る。
すると、背後から「後で後悔するぞ」という、脅すようなラヴァルの声が聞こえてきたから、小夜子も黙ってはいない。一瞬の迷いもなく、彼のぎりぎりのところを狙って銃弾を撃ち込むと、鋭い眼差しで「このあたりには誰も住んでいない。いくら叫んでも、助けは来ないわ」と吐き捨てた。アルベールと小夜子が出会ったのは3ヶ月前。娘の死のショックで精神を病み、小夜子が勤める病院に通院していたアルベールに、「私は 心療内科の医師です。5分ほどよろしいですか」と小夜子が声をかけたのが最初だった。そのときのことを思い出しながら、「結局、君まで巻き込んでしまった。どんなに感謝すればいいか」とアルベール。「いよいよね。ふたりで最後までやり遂げましょう」という小夜子の声にも力が入る。
彼らは本気だった。ラヴァルが「トイレに行かせてくれ」と叫んでも、失禁しても放置し続け、空腹を目で訴える彼の前でプレートに乗った料理をぶちまける酷い仕打ちを続けたのだ。そんなある日、過酷な状況に耐えきれなくなったのか、ラヴァルから驚きの証言が飛び出す。ミナール財団には有志たちが作った孤児院のような児童福祉が目的のサークルがあって、ラヴァルは「集められた子供たちはどこかに売られていったのではないか?子供たちを売買して売れ残ったら始末する、そんなことができる黒幕は財団の影の実力者ピエール・ゲラン(グレゴワール・コラン)しかいない」と主張したのだ。だが、鵜呑みにはできない。ラヴァルから聞き出したピエールが潜伏する山小屋に向かったアルベールと小夜子は、猟師と一緒に山から帰ってきた彼を脅し、拘束。ピエールの入った寝袋を引きずりながら、猟師の追撃を振り切るように森林、丘陵地帯を駆け抜け、隠れ家に戻ると、ラヴァルの横の鎖にピエールを繋いでふたりを突き合わせる。するとやがて、彼らの口から、それまでのすべての出来事を覆す衝撃の真実が浮かび上がってきて…。 果たして、アルベールの娘マリーは、誰に、なぜ殺されたのか。事件の思いがけない首謀者とは─。
国境を越えた“徹底的復讐劇”の先に待つ真実とは──Cast






Director


Production Note
- 『蛇の道』をフランスでリメイクした黒沢清監督の思い
-
 フランスの映画制作会社、CINEFRANCE STUDIOSが日本の映画監督との仕事を熱望していることを知った黒沢清監督が、「『蛇の道』をフランスでリメイクしたい」と即答したのが全ての始まりだった。オリジナルの『蛇の道』は、哀川翔と香川照之が共演した1998年のVシネマ(ビデオ映画)の傑作。小学生の娘を殺害され、復讐に燃える宮下(香川)と彼に協力する新島(哀川)の動向を描いたサスペンス・ミステリーだったが、黒沢監督は「高橋洋がオリジナル脚本で書いた復讐劇の設定が秀逸で、あの物語を限られた映画ファンしか観ないVシネマだけに終わらせるのは勿体ないと以前から思っていたんです」と語る。
フランスの映画制作会社、CINEFRANCE STUDIOSが日本の映画監督との仕事を熱望していることを知った黒沢清監督が、「『蛇の道』をフランスでリメイクしたい」と即答したのが全ての始まりだった。オリジナルの『蛇の道』は、哀川翔と香川照之が共演した1998年のVシネマ(ビデオ映画)の傑作。小学生の娘を殺害され、復讐に燃える宮下(香川)と彼に協力する新島(哀川)の動向を描いたサスペンス・ミステリーだったが、黒沢監督は「高橋洋がオリジナル脚本で書いた復讐劇の設定が秀逸で、あの物語を限られた映画ファンしか観ないVシネマだけに終わらせるのは勿体ないと以前から思っていたんです」と語る。
黒沢監督の提案に、CINEFRANCE STUDIOSのプロデューサーもオリジナル版を観た上で「面白い!」と瞬時に反応。「監督がそこまではっきり『やりたい!』と言うからには、何かあると思ったのでしょう」と、小寺剛雄プロデューサー(以下小寺P)も強調する。「ミニマルな作品ですけれど、場所や設定を変えるだけで広がるようなポテンシャルを感じさせる。監督の演出メモにも『リメイクではなく完全版』と書かれていましたが、この数奇な復讐劇をしっかりと完成させたいという黒沢監督の強い思いがフランス側にも伝わったんだと思います」
オリジナル版との大きな違いは、舞台が東京からフランスのパリに、主人公が男性の教師から女性の心療内科医に変わっているところだ。黒沢監督は「脚本の初期の段階から主人公を日本人の女性にしたいと思っていましたが、深い考えがあってのことではないです。『ダゲレオタイプの女』(16)を以前フランスの俳優たちで撮ったので、あのときとは違う経験をしたくて、そうしたような気がします」とつけ加える。「ただ、僕自身分析はできていませんが、結果的に、フランス人の男性たちの中に日本人の女性がひとりいるという構図になったことで、一見弱々しく見える彼女が実は全てをコントロールしているのではないか、という雰囲気が強くなったような気がします」
- 柴咲コウが鋭い眼差しのミステリアスなヒロインに
-
 主人公の心療内科医・新島小夜子に、黒沢監督たっての希望でキャスティングされたのが柴咲コウだ。「彼女はあの目つきがいいですよね。あの目で見つめられただけで、男性はあらぬ方向へと誘導されてしまう気がする。全編フランス語のセリフなので引き受けてくれるか心配だったんですが、一か八か声をかけさせてもらったら、『だからこそやりたい!』と快諾していただけたんです」と黒沢監督。その言葉を受けるように、柴咲が「『なぜ私なんでしょう?』と監督に最初に聞いた覚えがあります(笑)」と振り返る。「20代、30代の私は特に“動き”のある役が多かったので、小夜子のようにミステリアスで物静かな役でのオファーが意外だったんです。ただ、何を考えているのか分からない小夜子を、物語の進行とともに垣間見られる彼女の本心の見せ方を考えながら、観客を最後まで引きつけられるキャラクターにしていくことに次第に興味が湧いてきて。フランス語に挑戦できることにも喜びを感じたので、出演させていただきました」
主人公の心療内科医・新島小夜子に、黒沢監督たっての希望でキャスティングされたのが柴咲コウだ。「彼女はあの目つきがいいですよね。あの目で見つめられただけで、男性はあらぬ方向へと誘導されてしまう気がする。全編フランス語のセリフなので引き受けてくれるか心配だったんですが、一か八か声をかけさせてもらったら、『だからこそやりたい!』と快諾していただけたんです」と黒沢監督。その言葉を受けるように、柴咲が「『なぜ私なんでしょう?』と監督に最初に聞いた覚えがあります(笑)」と振り返る。「20代、30代の私は特に“動き”のある役が多かったので、小夜子のようにミステリアスで物静かな役でのオファーが意外だったんです。ただ、何を考えているのか分からない小夜子を、物語の進行とともに垣間見られる彼女の本心の見せ方を考えながら、観客を最後まで引きつけられるキャラクターにしていくことに次第に興味が湧いてきて。フランス語に挑戦できることにも喜びを感じたので、出演させていただきました」
- 日仏の演技派俳優たちが黒沢清ワールドに集結
-
 ジャーナリストのアルベール・バシュレに扮したダミアン・ボナールは、『レ・ミゼラブル』(19)の彼を見た黒沢監督が「この俳優、面白いなと思って」とオファー。すぐに「やりたい!」というリアクションがあったようだが、自らの勘を信じた黒沢監督の狙いは的中。「彼は情緒不安定なアルベールになりきるため、撮影中はなるべく眠らないという自らのアプローチを徹底させていたし、共演相手へのリスペクトを忘れない。柴咲さんの役が如何に大変なのかも分かっているので、彼女を気遣い、ホン(台本)読みにも何度も付き合っていた。ふたりの関係性がいい化学反応を起こしていると思います」(小寺P)。柴咲は、「私がフランス語のセリフに不安を抱えていたので、たくさんお付き合いしてもらいました。優しくて、包容力のあるボナールは快く引き受けてくれて。フランス語と日本語のセッションにもなり、ひとつひとつのセリフや動きについてお互いの意識のすり合わせができたのはよかったです」
ジャーナリストのアルベール・バシュレに扮したダミアン・ボナールは、『レ・ミゼラブル』(19)の彼を見た黒沢監督が「この俳優、面白いなと思って」とオファー。すぐに「やりたい!」というリアクションがあったようだが、自らの勘を信じた黒沢監督の狙いは的中。「彼は情緒不安定なアルベールになりきるため、撮影中はなるべく眠らないという自らのアプローチを徹底させていたし、共演相手へのリスペクトを忘れない。柴咲さんの役が如何に大変なのかも分かっているので、彼女を気遣い、ホン(台本)読みにも何度も付き合っていた。ふたりの関係性がいい化学反応を起こしていると思います」(小寺P)。柴咲は、「私がフランス語のセリフに不安を抱えていたので、たくさんお付き合いしてもらいました。優しくて、包容力のあるボナールは快く引き受けてくれて。フランス語と日本語のセッションにもなり、ひとつひとつのセリフや動きについてお互いの意識のすり合わせができたのはよかったです」
ミナール財団の元会計係ティボー・ラヴァルに扮したマチュー・アマルリックに至っては、黒沢監督が本人に自ら出演交渉をした。「マチューが『彼女のいない部屋』(21)のプロモーションで来日したときに直接お願いしたんです。『どんな役なんだ?』って聞くから、『とんでもなく悪い奴で、殺される役だ』って言ったら、『それはやりたい。そういう、最初に殺される役をやりたかったんだ』って気軽に友だち感覚で引き受けてくれました」と黒沢監督は悪戯な笑みを浮かべる。「ただ、撮影が実際に始まると、『すぐ死ぬと思っていたのに、けっこう長く生きているんだね』ってこぼすから、『いやいや、けっこう最後の方まで出演してもらいます。死んでもまだ死体として出てきますからね』って説明したんです(笑)」
小夜子の患者・吉村に扮した西島秀俊について、「以前からの付き合いで、スケジュールを空けてくれて、1日だけのパリの病院での撮影にかけつけてくれました」と黒沢監督。小夜子の夫・宗一郎を演じた青木崇高との奇跡的な縁についても述懐する。青木は黒沢監督の『旅のおわり世界のはじまり』(19)のウズベキスタンの撮影現場を訪ねたことがあり、黒沢監督は宗一郎役を考えたときに真っ先に青木を思い浮かべたという。「けれど調整が難しく、フランス在住の日本人俳優にお願いすることになったんです。ところが、その俳優が撮影直前に東京に戻ってしまって。彼を日本から呼び戻すというので、「だったら、青木さんに来てもらえばいいじゃないですか』と僕が口を挟んだんです。撮影数日前に連絡してもらったら、何とか調整してくれて、撮影前日にひとりでひょいとやって来てくれました。本当に助かりました」
- ハイレベルな芝居がフランス人のスタッフを魅了
-
 撮影は2023年4月中旬からパリとその近郊で5週間に渡って行われた。クランクインの最初の撮影は、吉村が小夜子の診察を受けるシーンだ。「黒沢監督は『フランス映画なのに、初日は日本語か~』って冗談っぽく言っていましたが、『ドライブ・マイ・カー』(21)が話題になった直後だったので、西島さんが現場に現れると、フランス人スタッフの間にどよめきが起きて。普段は穏やかな彼がカメラが回るとぶっきらぼうで、エキセントリックな吉村に変わり、程よい緊張感がありました。日本語のシーンとはいえ、あの一連のシーンでみんなが現場の空気を掴むことができたと思います」(小寺P)。柴咲も振り返る。
撮影は2023年4月中旬からパリとその近郊で5週間に渡って行われた。クランクインの最初の撮影は、吉村が小夜子の診察を受けるシーンだ。「黒沢監督は『フランス映画なのに、初日は日本語か~』って冗談っぽく言っていましたが、『ドライブ・マイ・カー』(21)が話題になった直後だったので、西島さんが現場に現れると、フランス人スタッフの間にどよめきが起きて。普段は穏やかな彼がカメラが回るとぶっきらぼうで、エキセントリックな吉村に変わり、程よい緊張感がありました。日本語のシーンとはいえ、あの一連のシーンでみんなが現場の空気を掴むことができたと思います」(小寺P)。柴咲も振り返る。
「吉村によって小夜子のキャラクターも浮き彫りになる部分がありますよね。疑心暗鬼になって、周りの人間が全て敵に見える彼と、白衣を着て、優しい口調で冷静に対処する小夜子。そんな相容れないものを纏ったふたりを、良い距離感で表現できたような気がします」小夜子を演じた柴咲コウの渾身の芝居も、監督や現地のスタッフの想像を超えるものだった。柴咲は日本にいるときからフランス語の指導を受け、現地でも、撮影に入ってからもレッスンを続けていたというが、「最初のホン読みのときに、彼女のフランス語のセリフを聞いたスタッフの顔が“お!”という驚きに変わりました」と小寺Pは興奮気味に語る。「小夜子が喋るのはネイティブの人が話す完璧なフランス語ではなくて、フランスに移住して10年ほど経った日本人が話すようなフランス語でなければならなかったんですが、それを完璧に習得していましたからね。200以上セリフがありましたが、NGはほとんどなくて」。
柴咲はフランス語だけではなく、パリ滞在中の2ヶ月間はマルシェに行って店員と会話をしたり、東京と同じように自転車を乗り回し、小夜子の日常を身体に自然に馴染ませていった。「普段から体幹を鍛えられているので身体能力も抜群」(小寺P)。黒沢監督も驚きを口にする。「実は、柴咲さんがアクションをどこまでできるのか正直分からなかったんです。でも、やってみたらスゴくて。相手を押さえ込んだり、物を投げる動きが動物のように俊敏で、獰猛な感じがする。それこそ、車に乗って発車させるまでの速さは映画史上最速です(笑)。シートベルトを締めてからエンジンをかけ、ギアを入れて出発する動作は、誰がやっても時間がかかるんです。ハリウッド映画でも編集で大抵ごまかしているんですが、柴咲さんはとても速く、ワンカットで撮ることができたんです」 。「それでいて、休憩時間中はみんなと一緒に食堂でご飯を食べ、談笑される。フランス人キャストやスタッフも彼女を尊敬の眼差しで見ていたと思います」(小寺P)小夜子の夫・宗一郎に扮した青木崇高については、「脚本の段階から、『表情だけでこの難しいニュアンスを伝えられる俳優がいるのか?』と感じていたスタッフもいたはず。でも、『なあ、小夜子…』と言った後の青木さんの表情がス~っと変わっていくのを見た瞬間、モニター前のスタッフからは『ウワ~』と唸り声」(小寺P)。柴咲は「監督が敢えてそうされたのでしょうが、青木さんが同じパリでの撮影に参加されていたので安心感がありました。たった1日だけの撮影でしたが、夫婦として一緒にいた空気を私たちは当然作り出さなければいけなくて。青木さんはそれをつかみ取るのがお上手だったので、私も小夜子としてそこに乗っからせていただいたところがあります (笑)」
- リスペクトと奇跡に溢れた黒沢清監督の撮影現場
-
 黒沢監督の現場はいつもスピーディに撮影が進んでいくが、舞台をフランスに移しても変わらない。俳優にそのシーンの動きだけを説明し、細かい心情や芝居に関する演出をしないのもいつも通りだ。黒沢組初参加の主演の柴咲は、「クランクイン前に監督にいろいろ質問してしまったのですが、浅はかだったなと。言葉にならないものを画で伝えるのが映画ですし、その複雑なものを汲み取って表現するのが俳優なんだということに改めて気づかされました」。その上で「黒沢監督の映画は、生身の人間と機械的なものとのバランスが絶妙で」と、黒沢ワールドの住人に初めてなった印象を告げる。「無機質な倉庫みたいな隠れ家を引きの画で撮る一連のシーンでは、ピチョンといった水の音も機械的なものに感じるから、そこをそれぞれの思いを抱えた人間が歩くと、生々しさと硬さが相まって独特な不穏な空気になるんです」。俳優の芝居に絶大な信頼をおいている黒沢監督は、「全てのシーン、画が明確で、迷いがないんです」と小寺Pも続ける。かと言って、自分のイメージだけに凝り固まるのではなく、意見やアイディアもきちんと聞くという。
黒沢監督の現場はいつもスピーディに撮影が進んでいくが、舞台をフランスに移しても変わらない。俳優にそのシーンの動きだけを説明し、細かい心情や芝居に関する演出をしないのもいつも通りだ。黒沢組初参加の主演の柴咲は、「クランクイン前に監督にいろいろ質問してしまったのですが、浅はかだったなと。言葉にならないものを画で伝えるのが映画ですし、その複雑なものを汲み取って表現するのが俳優なんだということに改めて気づかされました」。その上で「黒沢監督の映画は、生身の人間と機械的なものとのバランスが絶妙で」と、黒沢ワールドの住人に初めてなった印象を告げる。「無機質な倉庫みたいな隠れ家を引きの画で撮る一連のシーンでは、ピチョンといった水の音も機械的なものに感じるから、そこをそれぞれの思いを抱えた人間が歩くと、生々しさと硬さが相まって独特な不穏な空気になるんです」。俳優の芝居に絶大な信頼をおいている黒沢監督は、「全てのシーン、画が明確で、迷いがないんです」と小寺Pも続ける。かと言って、自分のイメージだけに凝り固まるのではなく、意見やアイディアもきちんと聞くという。
「『じゃあ1回やってみよう』、『それは面白い』と採用することも。アイディアのかぶせ合いが面白い作品を生み出すことに繋がっていったような気がします」。 黒沢監督はスタッフやキャストに「オリジナルの『蛇の道』は観ないでください」と告げ、撮影監督(アレクシ・カヴィルシーヌ)とも細かい打ち合わせはしていない。「それでも、オリジナルを踏襲したような構図のシーンになるのには驚きました。監督と撮影監督のケミストリーが起きたような気がします」(小寺P)。奇跡的瞬間が撮影中にはまだまだあった。「黒沢監督が日本語で指示を出すと、通訳を介していないのに、助監督が『分かった』と指示通りのことをすることがあって(笑)。監督は『言葉が通じなくても、分かる人はいるんですよ』と。あの瞬間は人間の繋がりの強さを感じました」と小寺P。「天気も味方をしてくれました」と柴咲が引き継ぐ。
「旅行や別の仕事で私がパリに行ったときはいつも晴れるんですが、黒沢監督の現場ではグレーと言うか、いつも曇天で、黒沢仕様の空模様だったような気がします(笑)。冒頭のシーンも雨が降って、それがピタッと止んだときに撮影したので、太陽がちょうど雲にかかって、建物や地面が暗い色合いになったんです。晴天だったらあのような雰囲気にはならなかった、天気も本当に絶妙なバランスでした。それも含めて、黒沢監督は言葉では言い表せられない、人間の複雑さ、曖昧さを表現されるのに長けた、本当に素晴らしい方だと改めて感じました」